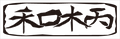禾口木丙のマフラーは、手描き友禅、手捺染友禅(板場友禅)など古き伝統を踏襲しつつ新しい技術を交えた手法で、一枚ずつ丁寧に染め上げております。
ここでは、伝統的な京友禅について長年現場で関わってきた職人が、伝統的な友禅染やデジタルを取り入れた友禅染について解説します。
そもそも友禅染めとは?
友禅染め(ゆうぜんぞめ)は、日本の伝統的な染色技法の一つで、昔から着物や帯を絢爛に彩る装飾として発達しました。
江戸時代の絵師・宮崎友禅斎が考案し、その名が冠せられたとされます。
友禅染めは、自由で華やかなデザインが特徴。自然の風景や花、鳥などがモチーフにされることが多いのは、自然や生き物にこそ美が宿るということでしょうか。
染色の際には、まず糊で模様を描き、その上に染料を重ねて描く伝統的な手法や、手描きで直接模様を描く「手描き友禅」があります。
現在でも、京都や金沢を中心に受け継がれており、高級着物や工芸品として国内外でよく知られています。
伝統的な友禅の工程
下絵(あたり)
青花を水で薄めた液で大まかなあたりをつけます。
下絵(本描き)
あたりに沿って濃い目の青花で本描きしていきます。
糊置き(糸目)
もち糊を柔らかくしたのりで、防染の役割をする糸目糊を置いていきます。現代になってゴムを糸目にする場合がありますが、これは主に後友禅の場合です。
挿し友禅(塗り)
糸目糊を生地に浸透させるために豆とふのりで地入れをした後、模様の中に色を入れていきます。これが友禅です。
蒸し(釜蒸し)
友準の染料を定着させるには、約90度の釜の中で約40分蒸します。
伏せ(糊伏せ)
蒸しの後は柄の上に伏せ糊にて伏せて、柄に地色が入らないようにします。
引き染め
引き染めにて、地色を染めます。
蒸し水元(水洗)
その後、再び、蒸しをして糸目糊、伏せ糊ともに水で洗い流します。これが水元です。
金彩
ゆのしをして生地を整理した後は、金彩で縁くくりをしたり、金箱で煌びやかに演出します。
筆で下絵と同じように金で絵を描く金彩友禅もあります
刺繡
その後、刺繍をして、全ての工程の仕上がりです。
伝統手法に新しい技術を交えた「デジタル京友禅」の工程
下絵 (あたり)
下絵の工程は、生地か紙かという違いで、全て手で 描いていきます。

下絵(本描き)
デジタル友禅の場合は、まずは、紙の上に鉛筆にて あたりを描き、その後にペンや筆で本書きします。

転写(読込み)
下絵の絵は高性能なスキャナーで読み取 ります。 読みとった下絵はコンピュータ上で糸目として、手描き で修正を加えていきます。

糊置き(糸目)
手法は違えど、やっていることは手描きの糊置き そのものです。

挿し友禅(塗り)
修正が加えられた糸目に一つずつ彩色を施します。 デジタルの技術を最大限に活用して筆なども色々な ものを使って手描きで友禅していきます。
配色は全体のバランスを考えながら丁寧に友禅していきます。


引き染め
ぼかしが必要なものは丁寧に感覚良くあげていきます。 この時、地色も同時に決められ、色の調子を見ながら 画面上でできるのがデジタルならではです。

実際に生地へ
その後、インクジェット染めの機械にデータを入れ、 地入れ(下処理)した生地の歪みなどを補正しながら 染めます。

きちんと染まっているか、目視で確認しながら染め上げていきます。なお、この時の色は画面で作ったものとは全く異なります。蒸して初めてその色になります。

蒸し水元(水洗)
染料を定着させるための蒸し、余分な染料を洗い流す ための水元などは、どの友禅方法でも変わりません。 あと、機械で蒸し水元ができる、オープンソーパー もあります。

デジタル京友禅は、伝統を守りながらも現代のニーズに対応するための形と言え、その製品が今注目されています。